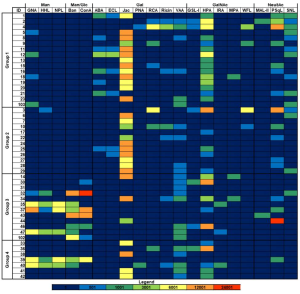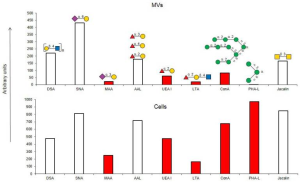2024年のノーベル物理学賞に甘利俊一先生が入っていないのは変だ
2024年のノーベル物理学賞をニューラルネットワークに貢献した2名の科学者が受賞したのは周知の事実です。
自分が富士通に在籍していた時期、ニューラルネットワークの先駆けとなる甘利俊一先生の論文を読み、将来のコンピューターとしての可能性を熱く仲間と語り合っていたことを思い出し、甘利先生が受賞者に入っていないことにとても違和感を覚えました。
因みに、当時のパソコンの能力では、ニューラルネットワークをソフトウェアーとして実現するには無理があり、ハードウェアーとしての構築を仲間とともに考えていました(笑)。
甘利先生の先駆的な研究:
1.A Theory of Adaptive Pattern Classifiers、1967年
2.Characteristics of randomly connected threshold-element networks and network systems、1971年
3.Learning Patterns and Pattern Sequences by Self-Organizing Nets of Threshold Elements、1972年
4.Characteristics of Random Nets of Analog Neuron-Like Elements、1972年