GlycoStationがいよいよ2007年9月にモリテックスより上市されました。営業活動の開始です。モリテックスにおけるバイオ事業関連の営業TOPは、塙部長でした。日本レーザー電子から移籍した営業部隊(奥村、江崎)も塙部長配下の竜野部長グループに配属されていました。糖鎖やレクチン関連の類似商品はそもそもマーケットに存在しておらず、モリテックスの営業マンも糖鎖プロファイラーやレクチンアレイの技術とその応用については無知ですし、完全にゼロからの販路開拓となりました。
研究所だからと「研究開発に没頭していれば良い」というだけの環境とは全く異なります。まずは、研究者自らが、技術や製品の特長を説明しつつ、マーケットを開拓していかねばならない状況であることをグライコミクス研の研究者全員が理解する必要がありました。販売目標も、一次案は研究所が作り、納得性を持って営業部に理解してもらい、共に動く必要があるのです。いや営業さんに動いて頂くのです。自分は、そもそも20年近くも半導体の世界にいたので、バイオ系、ましてや糖鎖とレクチンに関しては、SGプロジェクト繋がりを除けば全くコネクションはありませんでした。しかし、SGプロジェクトはNEDOが牽引する大きなナショナルプロジェクトですし、参加者(大学、企業)も多いので、まずはこのメンバーとその協力組織も潜在的な顧客に成り得ました。これは大きなプロジェクトに参画することのメリットです。
SGプロジェクト外のマーケットを切り開いていくには、営業効率を高めるためにも考えられるマーケットを想定して予め潜在顧客層を絞り込む必要があります。3つの領域に焦点を合わせました。ひとつはバイオマーカー探索、もうひとつはバイオ医薬品の糖鎖修飾、そして最後は再生医療です。日本の糖鎖とレクチンの世界には不思議な派閥関係が存在していました。下手に動くと、競合するグループから締め出しを食らってしまうリスクがあります。そこで、まずは産総研とも良好な関係を保っていて、糖鎖バイオマーカー研究では第一人者である阪大医学部の谷口先生に相談を持ち掛けました。彼は快く二人の先生を紹介して下さり、彼らといっしょに動いてみてはどうか?と指導してくださいました。一人は、同じく阪大医学部におられる三善先生、もう一人は岡山大医学部におられる和田先生でした。もう一つのルートは、自分が仕掛けたモリテックスとGeneticLabの事業協力関係から、GeneticLabの顧客ルートを共有させてもらうことでした。このルートからは、北海道情報大におられる中林先生とのつながりを起点にしました。三善先生は、潰瘍性大腸炎やクローン病のバイオマーカー探索、和田先生は尿からの糖尿病性腎症のバイオマーカー探索、中林先生は肝がんのバイオマーカーに着目されていました。
GlycoStationを世界のデファクトスタンダードにすべく、国内の営業開拓と同時に海外の営業開拓にも取り掛かりました。国内ですら知り合いが少ない中、海外の糖鎖やレクチンの研究者は全く知らない状態でしたので、Glycobiologyの国際会議の出席者リストや米国CFGのメンバーリストを突破口として、GlycoStationとLecChipに関する技術情報をメールで一名一名に配信しました。BCC配信で大勢に一気に送るなんて言うやり方はしませんでした。送り先の研究者のお名前を一人一人きちんと記載し、1対1の関係を作ろうとしたのです。反響はすぐに現れました。Scripps研究所、Burnham研究所、Stanford大学、Emory大学、Johns Hopkins大学、Harvard大学、NCI、NHI、Cambridge大学、UCL、そしてAcademia Sinica。中でも真っ先に返事を下さったのは、ScrippsとBurnhmanであり、かの有名なJames Paulson先生や、Hudson Freeze先生だったのです。「かの有名な」と言う修飾子をPaulson先生に付けましたが、実は当時は彼が何者かをも全く理解しておらず、返事をくれたやさしい研究者と言うだけの思い込みで突貫しました。
Paulson先生も「なんだか変だな」と思ったのでしょう。
「ひょっとして君、自分の事知らない?」って聞かれてしましました(笑)。
知らない事ほど強いことはありません。自分の返事を下さった先生方はことごとくこの分野ではbig nameだったようでして、もしそれを知っていたら、尻込みしちゃっていたかもしれません。
GSR1200の定価は、2,100万円に設定されていました。そしてLecChipの定価は45,000円でした。まだ世の中に存在しないこんな高価な装置をすんなり買ってくれるようなお金持ちはまずいません。そこで、販促開始当時は、消耗品であるLecChipを数十枚購入してもらうことを前提に、GSR1200を一定期間貸し出しする、そして、気に入ったら予算申請をして是非購入をお願い致します、是非論文の執筆もお長い致します、というスタイルを取りました。営業を海外展開するに際して、モリテックスの米国拠点と英国拠点の皆様には大いに助けて頂きました。米国については、モリテックスの米国営業をサポートしていたChris Dalton氏が積極的に加わって下さり、デモや展示会では大変お世話になりました。また、森田社長は、欧州がことのほかお気に入りということもあり、英国内の販促では一緒にCambridgeに行ったり、ドイツのWismarにあるモリテックスの所有地を一緒に見学し、
「どう、ここにバイオの欧州拠点を作らないか?」って夢のある話をして頂いたり、協力先になるであろうFraunhofer instituteを二人で訪問したりもしました。自分も欧州の販促はとても好きです。電車に乗って移動するのが旅情を誘って良いですよね。食堂車でワインを飲みながら、流れゆく景色を眺めていると、とても幸せな気分になるのです。

(森田社長とドイツへ)

(Wismarにあったモリテックスの所有地を森田社長と訪問)
営業活動は、メールのみでなく、実際に欧米での展示会にもモリテックスのブースを出しました。2007年には、Bostonで開催されたGlycobiology2007のSummit GlycoResearchのブースに相乗りさせてもらい、San Diegoで開催されたBio2008、Philadelphiaで開催されたISSCR2008、Barcelonaで開催されたISSCR2009などには単独でブース展示をしました。特に、Bio2008では、糖鎖関連事業の大きなイベントとしてJetro主催の糖鎖工学セッションが併設されたこともあり、平林先生、梅澤先生、住友ベークライトの藤原部長(現住友ベークライト社長)や大久保氏と共にプレゼンをさせて頂く機会を得ました。住友ベークライトとの関係がこれを機会に急速に深まっていきました。
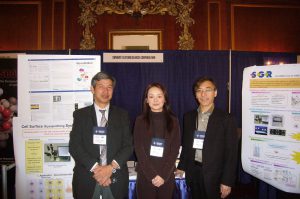
(Glycobiology 2007: Summit GlycoResearch (SGR)のブースに相乗り)

(BIO2008: 平林先生と齋藤)

(ISSCR2008: Chrisが応援に駆け付け)
このようにして、グライコミクス研究所が営業においても前面に立ってGlycoStationのマーケット開拓を全世界で進めていきました。富士通から転職後、日本レーザー電子の倒産という悲哀をなめた自分でしたが、眼前に新天地が広がったような高揚感を覚え、働いていることが楽しくてしょうがない時期が来ていました。

(La Jollaにて、Burnham Instituteでの大きな仕事の後、米国西海岸を楽しむ藤田、山田、そして金子)
この続きは「GlycoStation誕生秘話(4)」にて・・・・、
しかし、GlycoStationの全世界での拡販が思わぬトラブルを招きます。
そしてモリテックスにも思いもかけぬ問題が起ころうとしていました。